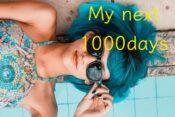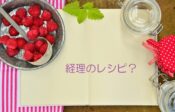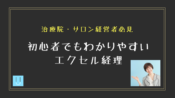知りたい数字はどの利益?5つの利益を理解する~売上総利益・営業利益・経常利益・税引前当期利益・当期純利益

税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。
こんにちは!税理士のうばとしこです!
クラウド会計などが徐々に世の中に浸透してくると、これまでのような「記帳代行業務」が徐々に減ってくると思われます。
「記帳代行業務」とは、お客様から通帳のコピーやcsvのデータ、請求一覧表などをお預かりして、伝票の起票を行うことです。
クラウド会計にも様々な種類がありますが、MFクラウドなどは、銀行口座の入出金、クレジットカードの利用履歴、現金出納帳の取り込みまで、インターネットで容易に取り込んでくることが可能です。
ですから「記帳代行業務」がAIによって無くなる仕事と言われるのかもしれません。
ところが、これは税理士が怯える状況なのか、といったらそうではないと思います。
むしろ、歓迎すべき時代がやってきた、と思っています。
なぜなら、これまで資料が届かない、という事態により申告がぎりぎりになってきたケースや、細かい入力ミスを探すためのロスタイムがなくなります。
これにより、本来の税理士としての役割、つまり、長年の経験によるアドバイスや、リアルタイムに作成した会計資料に基づいたフィードバック、節税対策の考案、改善点の提案、今後の課題の提供をすばやくできるようになるという大きなメリットがあるからです。
今までも、これからも、会計のスキルは必須
そのためには、フリーランサーの方、法人の社長、経理の担当者の方々はこれまで以上に会計の知識が必須になると思うのです。
なぜなら、数字は経営のヒントを物語っています。
記帳代行をAIに任せ、試算表の数字に表れてくる様々な数字の要因は、経営者でなければわからないことがたくさんあるからです。
数字にきちんと向き合っている経営者の方は、細かな知識ではなくとも、重要なポイントを理解されているため、情報を共有することが容易になっているのかな、と思います。
ぜひ、難しそうで嫌だな、と思わないでいただきたいです。
大きく発展している会社の経営者は、
必ずといっていいほど会計のスキルを重要視しています。
経理の担当者には会社の中で最も優秀な人材を備えるというのは、当然の配置とも言われています。
だからと言って社長自ら簿記や会計の知識を高めるのはなかなか難しいかもしれません。
そうは言っても、社長はポイントだけでも理解を深めていただきたいし、経理の担当者には高い会計のスキルを持っている方(もしくはスキルを磨くために努力できる方)を選んでいただきたいと思っています。
そこで今日は、損益計算書の5つの利益の特徴についてお話しします。
貸借対照表よりも、損益計算書の方がわかりやすいので5つの利益の特徴をつかめば、さらに面白いと思います。
実はこの利益の違いを理解するだけで、会社の“事情”を知ることができます。
これらの利益を理解していないと、安易に黒字なのか赤字なのかで評価してしまいがちです。
臨時収入によって黒字になっただけで、実は危機的状況にあるのを見逃していたり、本業では大きく利益を出しているからこのまま成長が見込まれるはずなのに、赤字だからという理由だけでやり方を軌道修正してしまったり・・・
これでは効率よく事業を発展させていくチャンスをみすみす逃してしまうことさえあるのです!
まずは利益の種類を知りましょう!
利益には、5つの種類があります。
1.売上総利益
2.営業利益
3.経常利益
4.税引前当期利益
5.当期純利益
です。
では、順番にその性質をみていきましょう!
1.売上総利益
これは、売上高から、仕入や外注費を差し引いただけの、いわゆる粗利益となります。
売上に直接対応する仕入、外注費だけが引かれているわけですから、利益率をざっくり見ることができる一番の入り口です。
粗利が何%確保できていればいいのか、ご自分の事業にあてはめてみてください。
また、この数字を月単位、年単位で比較して大きな差があるようだと要注意です。
ここの数字はあまり大きく変わらずに推移し、できればなだらかに上がっていくのが良いと思います。
2.営業利益
これは、1.売上総利益から、販売費及び一般管理費と呼ばれる“一般経費”を差し引いた数字です。
販売費及び一般管理費には次のような費用が含まれます。
・人件費
・水道光熱費
・通信費
・広告宣伝費
・地代家賃
・支払手数料
・保険料
・新聞図書費
・諸会費
・交際費
・消耗品費
・減価償却費
などです。
これは売上に直接対応しない(対応させることが困難な)経費も含まれています。
だからこそ、ほぼ毎期一定である場合が多いです。
大幅に人員を増やしたり、
出費のかさむ引越をしたり、
これまで行ったことのない広告宣伝にチャレンジしたり、
計画的に交際費を使って営業したり、
などなど、経営者や会社の内部の方でしか知り得ない、最も身近に取り扱っている情報が現れる費用です。
費用がもれていないか?先払いしていないか?なども振り返ってみると、その時の出来事が大きく反映されてくる数字でもあります。
この、営業利益が黒字であれば、本業は利益がでていると判断できる場合が多いです。
そのパーセンテージも頭に入れておくことで、リストラできる経費がないかを常に探し、無駄を省く体質に変わりやすくなるはずです。
3.経常利益
この利益は、上記の2.営業利益から、“営業外”の収益、費用を差し引いた金額です。
“営業外の収益”とはたとえば、
銀行などから受け取る受取利息、受取配当金や
所有している有価証券を売却した際の利益などです。
一方、“営業外の費用”とはたとえば、
借入返済のための支払利息や手形の割引料、
所有している有価証券を売却した際の損失などです。
要するに、本業とは関係ないけれど、お金が増えた、減ったという事象を表現して、その分を差し引いた結果の利益というところでしょうか。
営業外とはいえ、お金が動いているため、資金繰りには大きく影響してきます。
ですから営業利益よりも経常利益の方が、金融機関の融資担当者などが簡単な情報として取り入れることのも実態としてあります。
4.税引前当期利益
これは、上記の3.経常利益から、“特別な”利益や損失を差し引いた金額となります。
では、“特別な”とはどんなものでしょう。
特別利益といえば、たとえば
固定資産を売却して利益が出た、など、日常ではなかなか起こらない臨時の出来事などがあてはまります。
一方、特別損失といえば、たとえば
火災が起こった際の被害額など、日常では起こらない、特別な事情に基づくことがあてはまるわけです。
この、特別利益と特別損失を差し引けば、ほぼ完了ではあるのですが、こちらは文字通り“税引前”なので、まだ税金を引いていない金額です。
5.当期純利益
これぞゴール!とも言える、決算書の最も下に配置される利益です。
上記4.税引前当期純利益から、税金の額を差し引いた残りの金額となります。
まとめ
本当にざっくりと、簡単に見てきましたが、この5つの利益の違いがわかるだけでも、決算書から読み取れる情報量がぐっと増えてくると思います。
ぜひ今後は、5つの利益の違いを考えながら損益計算書を眺めていただけたら、と思います。
では、また!
.
税理士としてはまだまだ若手です。
お笑い大好き、やんちゃでマイウェイをゆく息子と男勝りで世話好きな娘がいます。子煩悩な夫と4人家族です。 学生時代から大好きだった街、吉祥寺に事務所を構えています。